「開業したはいいけれど、税金や経理って何から手をつければいいのか分からない…」
そんな不安を感じていませんか?
個人事業をスタートするときには、税務署や市区町村に提出すべき書類がいくつもあります。
しかし、ひとつひとつを調べるのは手間がかかり、期限をうっかり過ぎてしまうことも。
この記事では、開業時に必須の届け出を“分野別”に整理し、提出先・提出期限・書類の意味やメリットまでわかりやすく解説しています。
今すぐ全部理解しようとしなくても大丈夫。
まずは目次から、自分に関係がある手続きをチェックするだけでも、開業後のトラブルや損を防ぐことができますよ。
税務署に提出する書類
個人事業を開業したらまず提出!とりあえず出しておくべき2つの書類
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)
「これから事業を始めます」と国に知らせるための書類です。
出さなくてもすぐにトラブルになることは少ないですが、以下のような場面で提出が求められることがあります。
- 青色申告を受けるため(提出が必須)
- 屋号付きの銀行口座を作るとき
- 補助金や助成金を申請するとき
- 許認可が必要な事業を行うとき
「正式に個人事業主として認められる」という意味でも、できるだけ早めに提出しておくのが安心です。
▷ 提出情報まとめ
提出先:税務署
提出方法:e-Taxまたは書面(e-Taxが便利)
提出期限:開業から1ヶ月以内が推奨(※法的な提出期限はなし)
必要なケース:個人で事業を始めたすべての人
青色申告承認申請書
青色申告の特典(最大65万円の控除、赤字の繰越控除など)を受けるために必要な書類です。
今は会計ソフトを使えば要件を満たすのも簡単で、白色申告にも帳簿保存義務があることから、事業を始めた人は原則提出しておくべき書類です。
ただし、提出期限が厳密に決まっているため、出し忘れるとその年の青色申告ができなくなるので注意してください。
▷ 提出情報まとめ
提出先:税務署
提出方法:e-Taxまたは書面
提出期限:開業日から2ヶ月以内(※既に開業している人は、その年の3月15日まで)
※なお、期限後に提出してもその年分の青色申告は適用されません
必要なケース:青色申告を希望するすべての個人事業主
家族、他人に給料を払う場合に提出する書類
青色事業専従者給与に関する届出書
→ 青色事業専従者、要は自分の家族や身内に事業を手伝ってもらい、給料を出す場合には、この書類の提出が必要です。
これは「家族への給料を経費として計上するための事前の許可申請」のようなもので、支払金額や勤務内容が妥当であるかどうかを税務署に示す必要があります。
事前にこの届出を出していないと、家族への給与はどんなに実態があっても経費にできません。
あとから「出しておけばよかった…」とならないように、開業時や支給前に必ず提出しましょう。
▷ 提出情報まとめ
提出先:税務署
提出方法:e-Taxまたは書面
提出期限:
– 開業初年度:開業日から2ヶ月以内
– それ以外:その年の3月15日まで
必要なケース:家族に給与を払い、それを経費にしたい場合
⭐️ 実践チェックリスト(簡易版)
| チェック項目 | ✅ 確認ポイント |
|---|---|
| 👷♂️ 実際に働いているか? | 家族が事業に実務として関わっていること |
| 🕐 労働時間・仕事内容の明確化 | 何時間働いてどんな仕事をしているかを説明できる |
| 💰 給与額の妥当性 | 他人に同じ仕事を頼む場合と比べて妥当な金額か |
| 📅 支給のルール | 原則「毎月同額」を支払っているか(例:毎月25日に◯万円) |
| 📄 記録の保存 | 給与明細・振込記録・給与台帳などを残しているか |
📝 青色事業専従者給与の適用を受けるための要件(ざっくり解説)
・青色申告をしていること(大前提)
→ 白色申告ではこの制度は使えません。
・原則「毎月同額」で支払っていること
→ 年間支給額を月割りして、毎月定額支給するのが基本。
→ 支給日や支給額を届出書にも記載します。
・「専従者」としての条件を満たすこと
→ 以下すべてに該当する必要があります:
- 生計を一にする配偶者や親族
- 原則15歳以上
- 年間6ヶ月超、事業に専ら従事している
- 他の仕事をしていても事業がメインであること
・事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していること
→ 提出期限:
- 開業初年度:開業日から2ヶ月以内
- それ以外:その年の3月15日まで
・給与額が「適正」であること
→ 業務内容や地域の相場に照らして合理的な金額であること。
給与支払事務所等の開設届出書
給与を支払う事務所を開設した場合に、税務署に届け出る必要がある書類です。
たとえ従業員が1人だけでも、家族に給与を出す場合でも、支払いが発生するならこの届出が必要です。
提出すると…
・税務署内の源泉税担当部署
・住民税を所管する市区町村の担当課
などに情報が共有され、後日以下のような書類が届きます:
・給与支払報告書の提出依頼
・源泉徴収税の納付案内
=「給与支払事業者」として正式に認定される手続きです。
▷ 提出情報まとめ
提出先:税務署
提出方法:e-Taxまたは書面
提出期限:給与支払い開始から1ヶ月以内
必要なケース:誰か(家族含む)に給与を支払うすべてのケース
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
→ 原則として、給料を支払う事業者は、毎月10日までに源泉所得税を納める必要があります(例:6月分の給料の所得税は7月10日まで)。
しかし、毎月税務署へ納付するのは大きな負担。
そんなときに便利なのが、この「納期の特例」です。
この書類を出して承認を受ければ、源泉所得税の納付を年2回(1月・7月)にまとめることができます。
- 対象:従業員が常時10人未満の事業者
- メリット:年2回まとめて納付で、事務負担が軽くなる
- 注意点:申請しなければ適用されず、原則通り毎月納付が必要
▷ 提出情報まとめ
提出先:税務署
提出方法:書面のみ(e-Tax不可)
提出期限:随時(支払い開始前に出すのが望ましい)
必要なケース:給与の源泉徴収を年2回(7月と1月)にまとめて納付したい場合
消費税を払う場合に提出する書類
❗️注意
消費税は、制度として非常に複雑です。
各届出には厳密な提出期限があり、一度出したら2年間は取り消せないなど、メリット・デメリットが入り組んでいます。
そこまで不安に思う必要はありませんが、 「絶対に損したくない!」という方は、専門家に相談するか、ある程度仕組みを勉強してから提出するのが安心です。
課税事業者選択届出書
→ 本来、開業初年度は売上1,000万円以下であれば「免税事業者」として、消費税の納税義務がありません。
しかしこの届出を出すと、あえて自分から「課税事業者」になることができます。
たとえば以下のようなケースでは、この届出を出すことで消費税の還付が受けられる可能性があります:
- 輸出業をしていて、売上には消費税がかからないが、仕入や経費で多くの消費税を払っている
- 開業初年度に高額な設備投資(例えば店舗や機材など)を行う
また、インボイス制度(適格請求書)の関係で、「仕入税額控除を受けたいからインボイス発行事業者とだけ取引したい」という事業者が増えています。
そのため、BtoBの業種では課税事業者になっておかないと、取引から外されるリスクもあります。
▷ 提出情報まとめ
提出先:税務署
提出方法:e-Taxまたは書面
提出期限:
原則:課税事業者になりたい「前課税期間の末日」までに提出
例:令和7年1月1日から課税事業者になりたい → 令和6年12月31日までに提出
開業1年目の場合:
開業日からその年の年末までが課税期間となるため、開業日から原則としてその年の末日までに提出すればOK
※ただし、インボイス登録と同時に課税事業者になる場合は、登録希望日の属する課税期間の初日までの提出が必要になる場合もあるため注意
必要なケース:売上1,000万円未満でもあえて課税事業者になりたい場合(インボイス発行のため等)
簡易課税制度選択届出書
→ 消費税の計算が簡単に!業種ごとの「みなし仕入率」で納税額をざっくり計算できる制度です。
消費税の計算って、本来は「売上で受け取った消費税」から「仕入や経費で払った消費税」を引いて納税額を出すんですが…
実際には、領収書や仕入の計上など、すごく手間がかかります。
そこで使えるのが「簡易課税制度」。
年間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、**あらかじめ決められた“みなし仕入率”**を使って、支払った消費税をざっくり計算できるようになります。
📌 誰におすすめ?
- 売上が5,000万円以下の事業者で
- **経費があまりかからない業種(サービス業など)**の場合、
実際よりも多く仕入税額控除ができるため、税額が安くなる傾向があります。
また、制度を使えば帳簿や領収書の整理が不要になり、計算がとてもシンプルになるので、
「申告って難しそうで不安…」という方にも向いています。
自分で申告するハードルもぐっと下がります。
⚠️ 注意点:還付は受けられない!
ただし、簡易課税を選ぶと消費税の還付ができなくなるという大きなデメリットも。
例えばこんな場合には、簡易課税は不利になる可能性があります:
- 輸出業などで「売上に消費税がかからず、仕入に消費税がかかる」ケース
- 開業初期で「店舗や機材に高額な設備投資をした」ケース
そういった人は、あえて課税事業者+原則課税を選び、消費税の還付を狙う方が有利です。
🗓 提出期限に注意!
一度提出すると、2年間は変更できないルールがあります。簡単に切り替えはできません。
原則:適用を受けたい課税期間が始まる前日までに提出
例:令和7年1月1日から簡易課税を使いたい → 令和6年12月31日までに提出
▷ 提出情報まとめ
提出先:税務署
提出方法:e-Taxまたは書面
提出期限:課税期間の開始前日まで
必要なケース:消費税を納める義務がある人で、計算を簡略化したい場合
適格請求書発行事業者の登録申請書(インボイス制度)
インボイス制度の登録を行うための書類。登録後は「インボイス番号」が発行され、請求書に記載することが義務付けられます。
インボイス制度とは、ざっくり言えば「取引先が消費税を控除できるようにする仕組み」です。あなたがインボイス発行事業者として登録されると、「インボイス番号」が付与され、それを請求書に記載することで、取引先が支払った消費税を経費として差し引けるようになります。
一方で、こちら側(あなた)は「課税事業者」として消費税の納税義務が発生するため、利益の中から消費税を納めなければいけません。つまり、取引先にとってはメリットがある反面、あなた自身には負担が増える可能性があります。
取引先との関係性や、売上規模、事業内容によってメリット・デメリットは大きく変わるため、「絶対に登録すべき」とは言い切れません。ただ、BtoB(法人向け)のビジネスをする人や、取引先から「インボイス発行できますか?」と聞かれる可能性がある人は、早めに検討するのがおすすめです。
申請は、国税庁のインボイス制度専用ページからオンラインで行います(e-Taxとは別画面)。登録完了後、「インボイス番号」が通知され、請求書に記載する義務が生じます。
▷ 提出情報まとめ
提出先:国税庁インボイス登録センター
提出方法:インボイス専用Webページ(e-Taxではなく別画面)
提出期限:登録を希望する日の前日まで
必要なケース:BtoB取引がある人で、取引先がインボイスを求める場合
社会保険関係
国民健康保険・国民年金の加入手続き
会社を辞めて開業すると、それまで勤務先を通じて加入していた「健康保険」や「厚生年金」の資格が自動的に失われます。そして忘れてはならないのが、国民健康保険・国民年金は原則として強制加入という点です。
つまり、「任意」ではなく、加入が義務づけられている制度です。にもかかわらず、これらは自動では切り替わらないため、自分で市区町村の役所に行って手続きする必要があります。
もし未加入のままでいると、医療費が全額自己負担になったり、将来の年金額が減る、もしくは無年金になるなど、生活に大きな影響が出る可能性があります。
手続きの際に必要なものは、以下のようなものが一般的です:
- 退職日がわかる書類(退職証明書や資格喪失証明書)
- マイナンバーカード
- 印鑑(自治体によっては不要)
役所によって細かな必要書類は異なるため、事前に確認してから行くとスムーズです。
開業準備で忙しい時期かもしれませんが、国保・年金は「生活の土台」です。忘れずに、優先して手続きを済ませましょう。
▷ 提出情報まとめ
提出先:住民票のある市区町村役所
提出方法:役所窓口(原則、本人が対面で手続き)
提出期限:退職から14日以内(※厳密な法的期限はないが、早めの手続きが推奨)
必要なケース:会社を退職して個人事業主として開業した場合
人を雇う場合の手続き
労災保険の加入手続き(人を雇うなら原則、加入が義務です)
労災保険とは、従業員が業務中や通勤中にケガや病気、事故にあった場合に補償するための制度です。これは「正社員に限る」と思われがちですが、パート・アルバイトであっても、1人でも人を雇えば強制加入の対象になります。
「自分の家族だからいいだろう」と思っても、たとえ身内でも、給与を支払って雇うなら加入義務があります。もし加入せずに事故が起きた場合、補償費用を事業主が全額負担することになりかねません。
手続きとしては、以下の書類を労働基準監督署へ提出します:
- 労災保険関係成立届(雇用を開始した日から10日以内に提出)
- 概算保険料申告書(年間の見込み給与額に応じて保険料を計算)
提出は書面での持参が原則で、電子申請には対応していない地域も多いです。
なお、加入しないと労働基準法違反になり、罰則や是正指導の対象となることもあるため注意が必要です。
人を雇うことを決めた段階で、できるだけ早めに動くようにしましょう。
▷ 提出情報まとめ
提出先:所轄の労働基準監督署
提出方法:書面(原則、郵送または窓口)
提出期限:従業員の雇用開始から10日以内
必要なケース:パート・アルバイトを含め、1人でも従業員を雇った場合
雇用保険の加入手続き
雇用保険とは、失業したときの「失業手当」や、スキルアップのための「教育訓練給付」などを受けるための制度です。これは正社員に限らず、アルバイトやパートであっても「週20時間以上かつ31日以上の雇用見込み」があれば加入が義務になります。
人を雇ったら自動的に適用されるわけではなく、事業主が手続きをしなければなりません。対象となる従業員を雇うときには、以下のような書類を所轄のハローワークへ提出します:
- 雇用保険適用事業所設置届(新たに人を雇った場合、事業所として雇用保険に加入する手続き)
- 被保険者資格取得届(従業員ごとに提出するもの)
なお、提出は基本的に書面での窓口提出です。電子申請にはマイナポータルやe-Govを利用する方法もありますが、はじめての方は窓口で相談しながら進める方が安心かもしれません。
手続きを怠ると、失業手当などが受けられなくなるだけでなく、法令違反として事業者が罰則を受ける可能性もあるので、早めに対応しましょう。
▷ 提出情報まとめ
提出先:所轄のハローワーク
提出方法:書面(原則、窓口または郵送)
提出期限:雇用開始から10日以内
必要なケース:週20時間以上の勤務・31日以上の雇用見込みがある従業員を雇った場合
社会保険(健康保険・厚生年金)加入手続き
法人なら強制加入。個人事業主でも条件次第で義務に。
社会保険とは、「健康保険」と「厚生年金保険」の2つをセットにした制度です。
まず大前提として、法人の場合は、たとえ社長1人だけの会社でも加入が義務付けられています。これは「会社」という法人格をもった時点で、原則として社会保険への加入が求められるためです。代表取締役1人の会社でも例外ではありません。
一方、個人事業主は任意加入が基本です。ただし、従業員を常時5人以上(サービス業など一部業種を除く)雇用している場合は、個人事業でも社会保険の加入が義務になる場合があります。
加入手続きには以下のような書類を所轄の年金事務所へ提出する必要があります:
- 新規適用届(法人設立や要件を満たした時)
- 被保険者資格取得届(加入対象の従業員ごとに)
社会保険料は、会社と従業員が半分ずつ負担するため、事業者にとってもコスト負担は大きくなります。しかし、福利厚生の充実は従業員の安心感や採用のしやすさにもつながります。長期的に見れば、信頼できる職場づくりの土台になる制度と言えるでしょう。
▷ 提出情報まとめ
提出先:所轄の年金事務所(日本年金機構)
提出方法:書面または電子申請(GビズIDを利用)
提出期限:法人設立日または加入義務が生じた日から5日以内
必要なケース:
個人事業主でも従業員が常時5人以上の事業所(※一部業種を除く)は強制加入
法人は原則として従業員の有無に関係なく強制加入
まとめ:開業後の手続きは「自分を守るための準備」
個人事業を始めるときには、税務署・役所・保険関連など、さまざまな手続きが必要になります。
正直、出さなくてもすぐにトラブルになるわけではない書類もありますが、「あとから困らないように」「損しないように」するための準備として、開業当初にきちんと整えておくことが大切です。
とくに次のようなポイントを押さえておきましょう:
- 税務署への届け出(開業届・青色申告承認申請書など)は、節税の基本です。
- 家族や従業員に給与を出すなら、事前の届出が必要。出さないと経費になりません。
- 消費税関連の制度(インボイス・簡易課税など)は複雑なので、ケースに応じて慎重に判断を。
- 社会保険や労働保険への加入義務は「人を雇うかどうか」が判断基準になります。
開業直後は事務手続きが多くて大変かもしれませんが、早めにやっておくことで、後から困らずスムーズな事業運営ができます。
不安な場合は、専門家に相談するのも一つの手です。
あなたの開業がスムーズに、そして実り多いものになることを願っています!
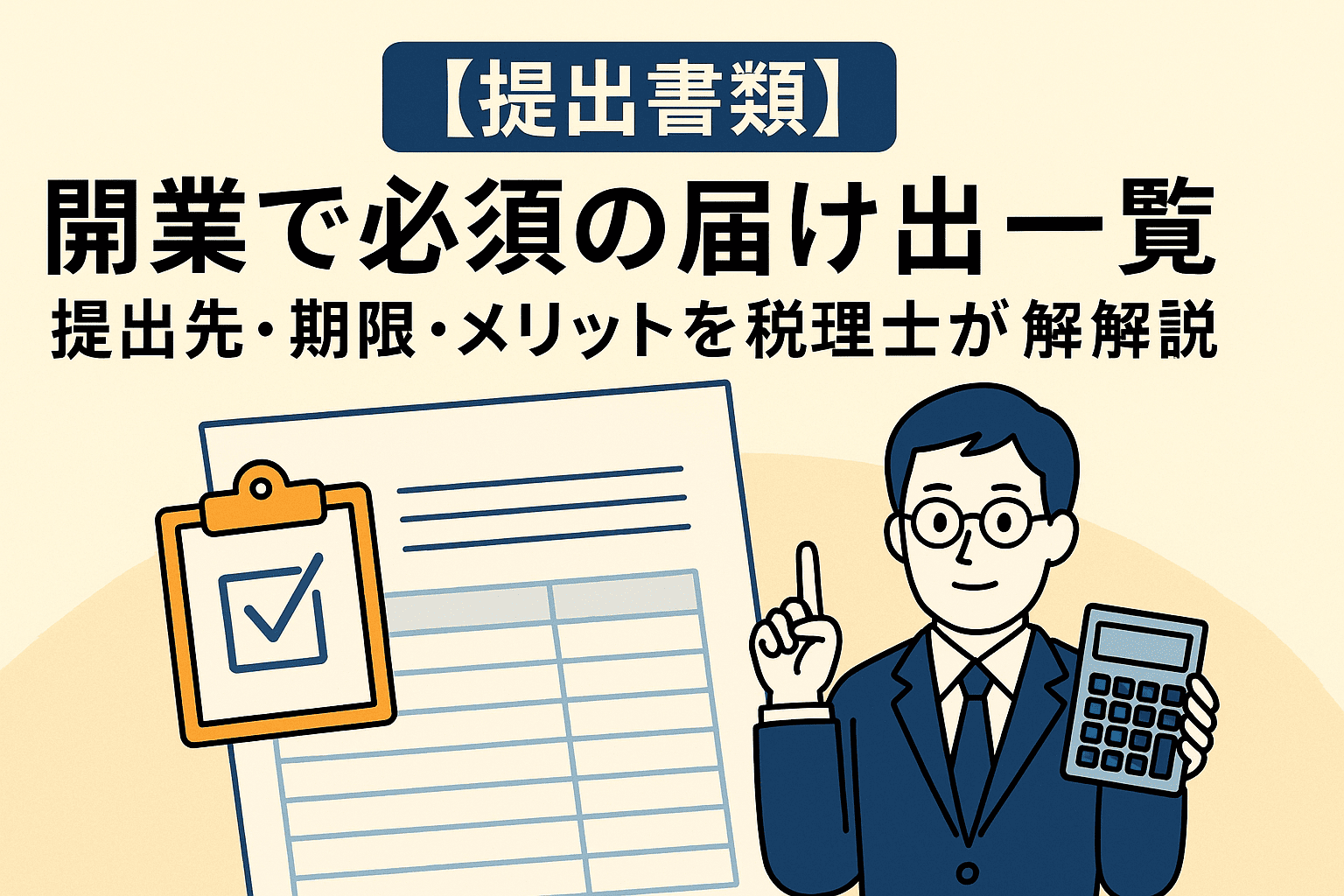
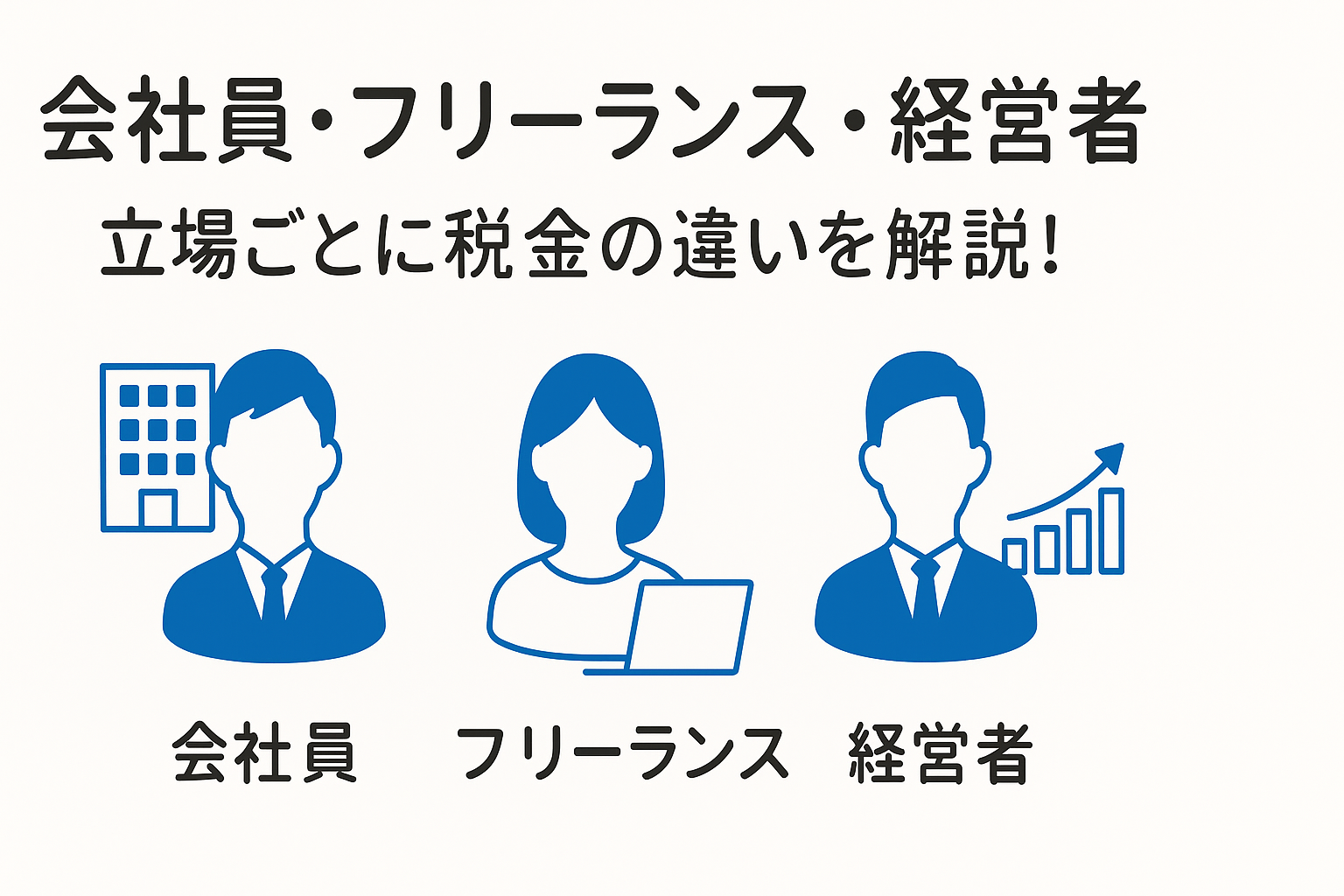
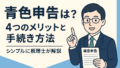
コメント