決算書って難しそう…そう感じている方も多いのではないでしょうか。でも実は、会計ソフトの力を借りれば、初心者の方でも決算書は作れるようになります。この記事では、仕訳の記帳から試算表の作成、決算整理、そして決算書の完成・申告までの流れを、初心者にもわかりやすく順を追って解説します。全体のイメージをつかめば、経理の不安もぐっと軽くなりますよ。
決算書ってそもそも何?なぜ必要なの?
決算書とは、1年間の事業活動を「数字」でまとめたレポートのようなものです。事業の利益や財産状況を正確に把握するために作成され、税務署への申告や銀行からの融資を受ける際にも必要になります。
「損益計算書」や「貸借対照表」といった書類が代表的で、これらを通じて会社の経営成績や財政状態が見えるようになります。難しく見えますが、全体の流れを知れば仕組みはシンプルです。
①まずは「日常の取引」を仕訳して記録する
取引の記録は、日々の経理の基本です。たとえば現金で売上があった場合、「現金」と「売上」という項目を使って記録します。これが「仕訳」と呼ばれる作業で、会計の第一歩です。
帳簿に正しく仕訳を記録することで、あとから損益や資産状況を正確に把握できます。最近では会計ソフトを使えば、取引内容を入力するだけで自動で仕訳してくれるので、初心者にも安心です。ただし、完全に任せきりにせず、内容の確認や勘定科目の選択ミスがないかは定期的にチェックすることが大切です。
②月末・期末にやる「残高確認」とは?
日々の記録が積み重なったら、月末や決算期に帳簿の内容を確認します。これが「残高確認」です。
現金の残高、預金の通帳、売掛金や買掛金の金額が、帳簿と一致しているかを照らし合わせていきます。ズレがあれば原因を探して修正します。
帳簿が正しく整理されていることが、正確な決算書作成の前提になります。会計ソフトを使えば、残高の自動照合もできて便利です。
③決算整理仕訳で「正しい利益」に整える
期末には、通常の取引とは別に「決算整理仕訳」という作業が必要です。これは、期間に応じた費用や収益を正しく反映させるための調整です。
たとえば、前払いした保険料を分割する処理や、使った分だけ減価償却する固定資産の処理が含まれます。こうした仕訳を加えることで、実際の利益や資産の状況が正しく反映されるようになります。
これもソフトを活用すれば効率的に対応できます。
④試算表を使って決算書のもとを作成する
整理した仕訳の集計結果を一覧にまとめたのが「試算表」です。試算表には、各勘定科目の金額が借方・貸方で整理されて表示されます。
この表を使って、数字に誤りがないかを確認します。借方と貸方の金額が一致すれば、基本的な記帳は問題なしという目安になります。
ここでズレがあれば原因を調べて修正し、最終的な決算書の土台を固めていきます。
⑤いよいよ「決算書」を作ろう
試算表をもとにして、いよいよ決算書を作成します。損益計算書では、収益から費用を引いて「利益」がどれだけ出たかを示します。
貸借対照表では、会社の「資産」「負債」「純資産」の状況が一覧でわかります。法人の場合は、必要に応じてキャッシュフロー計算書や株主資本等変動計算書なども作成しますが、個人事業主では通常ここまでの書類は不要です。
これらの書類は、金融機関に融資を申し込む場合や、株主への情報開示が必要な場面で使われます。会計ソフトを使えば、これらの書類はほぼ自動で作成されるため、初心者にも扱いやすいです。
⑥決算書ができたら申告書へとつなげよう
決算書を作成したら、次は税務署に提出する「申告書」を作ります。法人なら法人税、個人事業主なら所得税の確定申告が必要です。
申告書には決算書の内容を反映させる必要があり、提出期限や納税額の計算にも注意が必要です。期限に遅れると延滞税などのペナルティが発生するため、早めに準備を進めましょう。
e-Taxなどの電子申告システムも整っており、自力での対応も可能です。特に個人事業主にとっては、紙の申告よりも簡単に提出でき、還付処理も早いというメリットがあります。
⑦初心者でも決算書は作れる!まずは全体像を知ろう
経理の知識がまったくなくても、全体の流れを把握すれば決算書の作成はそれほど難しくありません。
今はクラウド会計ソフトが発達しており、仕訳や集計、決算書の作成まで多くの作業が自動化されています。
最初はわからないこともあるかもしれませんが、少しずつ進めれば大丈夫です。必要に応じて一部を専門家に相談しつつ、まずは全体のイメージをつかむことから始めてみましょう。
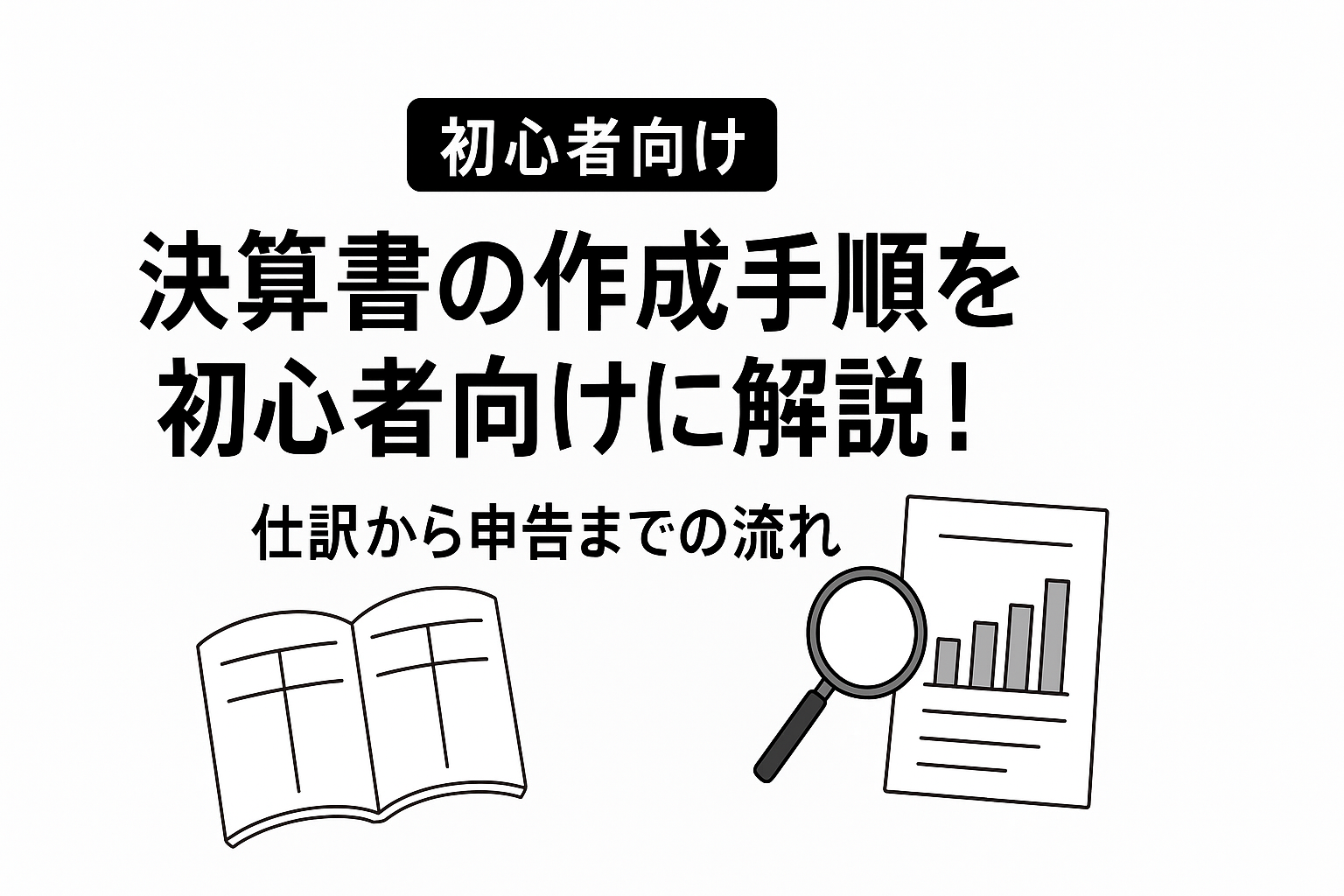
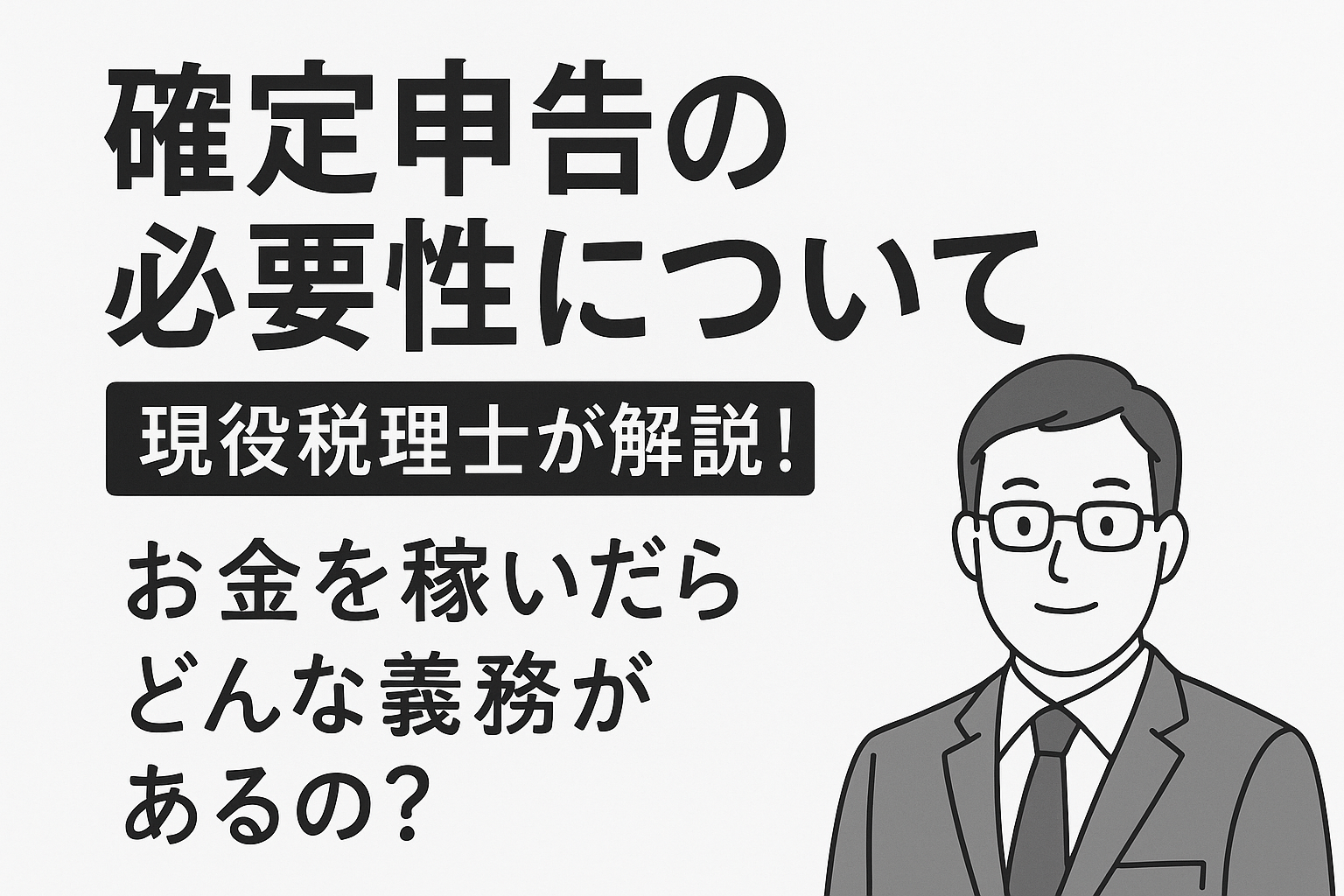
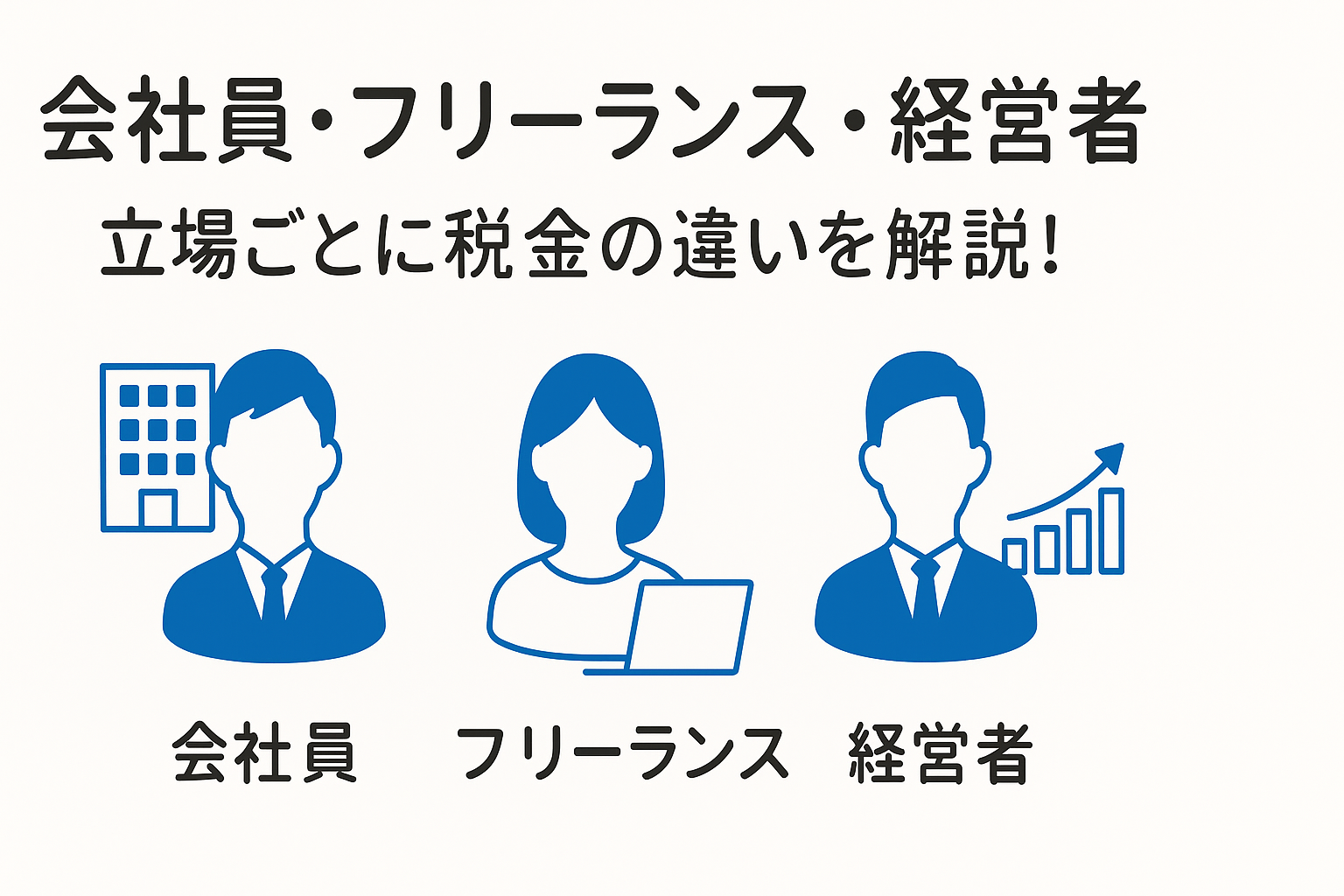
コメント